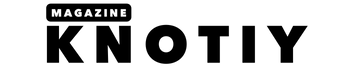犬のしゃっくりは、特に子犬によく見られる、飼い主にとってはお馴染みの現象かもしれません。その可愛らしい「ヒック」という音は、時に私たちを笑顔にしますが、犬の体内で一体何が起こっているのでしょうか?
また、しゃっくりが頻繁に起こる場合や、他の症状を伴う場合には、何か心配すべきことがあるのでしょうか?この記事では、犬のしゃっくりについて、その仕組みから原因、対処法、予防策、そして注意すべき点までを詳しく解説します。
しゃっくりの仕組みって?

犬の呼吸器系の構造は、私たち人間と非常によく似ています。私たちと同じように、犬にも胸部と腹部を隔てる横隔膜という筋肉があり、この筋肉が意識することなく呼吸を可能にしています。
通常、息を吸うときには横隔膜が収縮し、息を吐くときには弛緩します。しかし、この横隔膜が何らかの原因で痙攣すると、体は素早く空気を吸い込もうとし、その際に口から「ヒック」という音が出るのがしゃっくりです。
しゃっくりはあらゆる年齢の犬に見られますが、特に子犬に多く、成犬や老犬では比較的まれです。子犬の横隔膜を制御する神経である横隔神経は、まだ発達段階にあり、刺激を受けやすいため、しゃっくりが起こりやすいと考えられています。
また、子犬は好奇心旺盛で、口で世界を探求しようとするため、空気や食べ物を一緒に飲み込みやすく、これも横隔膜を刺激する一因となる可能性があります。
なぜ「ヒック」?一般的な原因を探る
犬がしゃっくりをする原因は一つではありません。日常生活の中でよく見られる要因がいくつかあります。
犬のしゃっくりの原因
- 早食い:勢いよく食べることで起こる刺激
食事や水を勢いよく摂取すると、食べ物や水分と一緒に大量の空気を飲み込んでしまうことがあります。この過剰な空気は胃を膨らませ、横隔膜を圧迫することで、しゃっくりを引き起こす可能性があります。 - 温度変化:冷たい空気の刺激
急激な気温の変化、特に冷たい空気を吸い込むことも、横隔膜を刺激してしゃっくりを引き起こすことがあります。 - 興奮やストレス:感情的な要因
興奮して激しく遊んだ後や、逆にストレスや不安を感じているときにも、呼吸が速くなることがあり、それが横隔膜の痙攣につながることがあります。 - 肥満:横隔膜への物理的な圧迫
肥満の犬は、過剰な脂肪が横隔膜を圧迫し、その機能を妨げることでしゃっくりを起こしやすくなる可能性があります。また、肥満は呼吸器系の他の問題を引き起こす可能性もあり、それがしゃっくりを誘発することもあります。肥満の犬は、過食が原因であることも多いため、食事のペースをコントロールすることも重要です。
しゃっくりが起きたらどう対処する?

犬のしゃっくりは通常、数分で自然に治まりますが、愛犬が苦しそうにしている場合は、以下の対処法を試してみると良いでしょう。
ゆっくりと水を飲ませる
少量の水をゆっくりと飲ませることで、横隔膜の痙攣が鎮まることがあります。
落ち着かせる
優しくなでたり、落ち着いた声で話しかけたりすることで、リラックスさせてあげましょう。
気を紛らわせる
遊びに誘ったり、おやつを与えたりして、しゃっくりから意識をそらしてみましょう。
マッサージ
胸や腹部を優しくマッサージすることも、横隔膜の緊張を和らげるのに役立つことがあります。
指を舐めさせる
これは一般的な対処法ではありませんが、犬によっては気を紛らわせる効果があるかもしれません。ただし、衛生面には注意が必要です。
愛犬のしゃっくりを予防するには?
愛犬のしゃっくりを未然に防ぐためには、日頃から以下の点に注意しましょう。
食事の量とペースを調整する
一度に大量の食事を与えるのではなく、少量を数回に分けて与えるようにしましょう。
早食いをする犬には、早食い防止用の食器を使用するのも効果的です。
一度にたくさんの水を飲ませない
特に興奮した後などは、水を一気に飲み干してしまうことがあるので、少量ずつ与えるように工夫しましょう。
ストレスの原因を軽減する
環境の変化や分離不安などがストレスの原因となる場合は、それらを取り除くように努めましょう
食事を落ち着いてゆっくり食べるようにする
食事を勢いよくかき込むように食べると、喉への刺激になったり、余計な空気を飲み込んでしまって胃が膨らんだりすることで、しゃっくりが出やすくなります。これを防ぐためには、以下のような工夫でゆっくり食べられるように促しましょう。手から少しずつ与える: 少量ずつなら早食いになりにくいです。早食い防止用の食器や知育トイを使う: 食べるのに時間がかかる仕掛けで、自然とゆっくりペースになります。
フードの種類や形状を変える
ドライフードの場合:ぬるま湯でふやかして、食べやすくする。ウェットフードや手作り食に切り替える:水分が多く、かき込みにくい場合があります。食事の量と回数を調整する: 一度にたくさん食べると胃が急に膨らみやすいので、1回の食事量を減らし、その分、食事の回数を増やして与えるのも有効です。
温度変化に気をつける
暖かい室内から寒い屋外に出たときなどに、温度差が原因でしゃっくりが出ることがあります。玄関など温度差が大きくない場所でいったん慣らしてから外に出るなど工夫してあげましょう。
寝ているときのしゃっくりは大丈夫?

犬も人間と同じように、寝ている間にしゃっくりをすることがあります 。特に子犬によく見られる現象で、成長とともに頻度は減っていくことが多いです 。
寝ている間のしゃっくりは、起きている時のしゃっくりと同様に、横隔膜の痙攣によって起こります 。しかし、なぜ寝ている時に起こりやすいのかについては、いくつかの説があります 。
リラックスしている可能性
寝ている間は体がリラックスしているため、呼吸がゆっくりになり、その際に空気を飲み込みやすくなることがしゃっくりにつながるという考えがあります。
自然な反射
しゃっくりは、まだ完全に発達していない子犬の呼吸器系の自然な反射であるという説もあります。子犬は、お母さんのお腹の中にいる時からしゃっくりをすることが知られており、これは呼吸に必要な筋肉の発達を促すための練習ではないかとも言われています。
夢を見ている?
まれに、寝ている間に見る夢が原因で、しゃっくりが出ることがあるという説もあります。特に、興奮するような夢を見た時に、呼吸が浅く速くなることが、横隔膜の痙攣を引き起こすと考えられています。
ほとんどの場合、寝ている間のしゃっくりは生理的な現象であり、特に心配する必要はありません。愛犬がぐっすり眠っていて、しゃっくり以外に特に変わった様子が見られなければ、そのまま様子を見て大丈夫でしょう。
しゃっくりに似た症状:見分けるためのポイント
しゃっくりと間違えやすい症状として、咳、くしゃみ、逆くしゃみがあります。それぞれの原因や特徴的な症状、見分け方を知っておきましょう。
しゃっくりと似た症状
- 咳
気道に異物や炎症がある場合に起こる、空気を強く吐き出す反射的な行動です。通常、「ゴホンゴホン」という音を伴い、病気やアレルギーなどが原因で起こることがあります。 - くしゃみ
くしゃみは、鼻腔内の刺激物(ほこり、花粉など)を排出するための反射です。「クシュン」という音と共に、鼻から勢いよく空気が排出されます。 - 逆くしゃみ
逆くしゃみは、通常のくしゃみとは逆に、空気を鼻から勢いよく吸い込む動作です。「ブーブー」というような鼻を鳴らす音が出ることが多く、短頭種(パグ、フレンチブルドッグなど)によく見られます。通常は無害ですが、頻繁に起こる場合は獣医に相談しましょう - 吐き気や嘔吐
犬が吐き気を感じているとき、お腹を何度かリズミカルに収縮させ(「ぱっこぱっこ」と動くように見えます)、最後に大きく口を開けて胃の中のものを吐き出そうとする動作をします。この一連の動きが、外見上しゃっくりと似ていることがあります。
実際に何も吐かなかったとしても、よだれがたくさん出ている口をしきりにペロペロと舐めているソワソワして落ち着きがないといった様子が見られる場合は、吐き気を感じているサインかもしれません。しゃっくりとは異なる状態の可能性があるため、注意深く様子を見てあげましょう。
心配のいらない犬のしゃっくりとそうでない症状

ほとんどの場合、犬のしゃっくりは一時的なもので、特に心配する必要はありません。しかし、以下のような症状が見られる場合は、獣医の診察を受けることを強くお勧めします。
頻度や持続時間の増加
もし愛犬のしゃっくりが、今までよりも頻繁に起こるようになったり、一度始まると1時間以上も続くような場合は、注意が必要です 。通常、犬のしゃっくりは数分から長くても15分程度で自然に治まることが多いからです 。
頻繁に繰り返されたり、なかなか治まらないしゃっくりは、何らかの体の異常を示しているサインかもしれません 。
併発する症状
しゃっくりに加えて、咳 、くしゃみ 、呼吸困難 、食欲不振 、嘔吐 、下痢 などの症状が見られる場合は、自己判断せずにすぐに獣医さんに相談してください 。これらの症状は、呼吸器系の病気(喘息、気管支炎、肺炎など) や、消化器系の問題 、心臓病 、熱中症など、様々な病気のサインである可能性があります。
中高齢になってからの頻度増加
特に今まであまりしゃっくりをしなかった犬が、中高齢になってから頻繁にするようになった場合は、注意が必要です 。これは、心臓病や呼吸器系の疾患 、あるいは喉や鼻の腫瘍 などが原因となっている可能性も考えられます。加齢とともに体の機能が低下し、様々な病気のリスクが高まるため、今まで見られなかった症状が現れた場合は、早めに獣医さんに診てもらいましょう。
愛犬の様子で少しでも気になることがあれば、自己判断せずに獣医さんに相談することが大切です。
まとめ
犬のしゃっくりは、多くの場合は生理的な現象であり、自然に治まるため過度に心配する必要はありません。しかし、頻繁に起こる場合や他の症状を伴う場合は、獣医に相談して原因を特定し、適切な対処を行うことが大切です。
日頃から食事の与え方やストレス管理に気を配り、愛犬の健康状態を注意深く観察することで、しゃっくりの予防につながります。