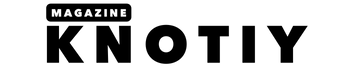分離不安症とは?
犬が飼い主と離れることに強い不安やストレスを感じ、問題行動を起こす状態を分離不安症と呼びます。これは単なるわがままやいたずらとして片付けられるべきではなく、犬の心に深く根ざした苦痛の表れとして理解する必要があります。飼い主さんがそばから離れると、犬は病的なまでに不安を感じ、その結果、様々な問題行動を引き起こしてしまう、心の病気の一つです。
分離不安症と単なる「寂しがり屋」との大きな違いは、その不安の現れ方にあります。寂しがり屋の犬は、飼い主さんが家を出る際に吠えることがあっても、その後すぐに落ち着き、飼い主さんの帰宅を待つことが多いようです。
一方、分離不安症の犬は、飼い主さんの姿が見えなくなった直後から強い不安を感じ始め、その不安は時間経過とともにピークを迎えます。つまり、飼い主さんと離れることで、犬は過度の不安やストレスを感じ、それが原因となって様々な症状が現れるのが分離不安症なのです。
効果的な治療を行うためには、犬がなぜそのような強い不安を感じてしまうのか、その根本的な原因を理解することが何よりも重要となります。
うちの子は大丈夫?分離不安症の兆候チェックリスト

愛犬の行動を観察し、以下の項目に当てはまるものがないか確認してみましょう。
| 留守中に見られる行動 | 飼い主さんと一緒にいる時に見られる行動 |
| 過剰な吠え、遠吠え、鳴き声 | 飼い主の後をついて回る、一人で外に出たがらない(ベルクロ・ドッグ) |
| 破壊行動(家具や物を噛む、引っ掻く、壊す) | 飼い主が出かける準備をすると落ち着きがなくなる |
| 排泄の失敗(普段はトイレでしない場所での排泄) | 飼い主の帰宅時に異常に興奮し、それが長く続く |
| 過剰なよだれ、震え | |
| 食欲不振(留守番前に与えたフードを食べない) | |
| 落ち着きのなさ(留守番中にずっとうろうろする、同じ場所をぐるぐる回る) | |
| 自傷行為(自分の体を噛む、舐め壊すなどして傷つける) | |
| 嘔吐、下痢 | |
| 床や地面を掘り続ける |
留守番中に激しく吠え続けたり、家具を噛んで壊したりする。特に、飼い主が出かけるときに窓のそばでずっと吠えたり、ドアを引っかく行動は分離不安の典型的なサインです。また、留守番前に与えた食事が手つかずになっている場合、分離不安の可能性が高いと考えられます。
このような行動が見られる場合は、分離不安症の可能性を考慮し、適切な対応を検討する必要があります。
犬が分離不安症になる原因ってなに?
犬が分離不安症になる原因は一つではなく、様々な要因が複雑に絡み合っていると考えられています。
| 原因 | 詳細 |
| 環境の変化 | 引っ越しやリフォーム、新しい家族(人間やペット)の加入、ペットの死、飼い主の生活スタイルの変化など、犬を取り巻く環境の大きな変化は、犬にとって大きなストレスとなり、不安を引き起こす可能性があります。特に、これまで常に誰かが家にいたのに、家族の就職や進学などで急に留守番の時間が長くなるようなケースでは、分離不安のリスクが高まります。 |
| 過去のトラウマ | 子犬の頃に親や兄弟と早期に離された経験や、虐待、ネグレクトといった過去の辛い経験は、犬の心に深い傷を残し、分離不安を引き起こす原因となることがあります。また、留守番中に大きな雷や地震、予期せぬ物音などを経験することも、トラウマとなり、飼い主さんがいない状況への強い不安につながることがあります。以前に捨てられた経験のある犬も、再び見捨てられるのではないかという不安から、飼い主さんへの過度な依存を示すことがあります。 |
| 飼い主への過度な依存 | 甘えん坊で寂しがり屋な性格の犬は、飼い主さんと離れることに強い不安を感じやすく、分離不安になりやすい傾向があります。また、飼い主さんが犬を溺愛しすぎるあまり、常に一緒にいたり、犬の要求に何でも応えてしまうような関係性は、犬の自立心を育む妨げとなり、飼い主さんへの過度な依存を生み出す可能性があります。飼い主さんの過剰な甘やかしは、犬に「不安を感じると助けてもらえる」というメッセージを与え、分離不安を助長する要因となることもあります。 |
| 生活スタイルの変化 | これまで在宅勤務だった飼い主さんが外勤になったり、家族構成の変化によって犬の世話をする人が変わったりするなど、生活スタイルの変化も犬にとっては大きなストレスとなり得ます。特に、コロナ禍以降、在宅で過ごす時間が増えた犬にとって、飼い主さんの外出は以前よりも大きな変化として認識され、分離不安を引き起こすケースも増えています。 |
| 単独飼育 | 他の犬との社会的な交流が少ない犬は、分離不安になりやすい傾向があるという報告もあります。 |
| シェルターからの引き取り | シェルターで過ごした経験のある犬は、過去の経験から再び見捨てられることへの不安が強く、分離不安を発症しやすい場合があります。 |
| 特定の人への執着 | 特定の飼い主さんに強い執着を示す犬は、その飼い主さんがいなくなると極度の不安を感じることがあります。 |
| トラウマとなる出来事 | 初めて長時間一人にされた経験や、留守番中に雷や花火などの大きな音に驚かされた経験などがトラウマとなり、分離不安を引き起こすことがあります。 |
| 加齢 | 高齢になると、視覚や聴覚などの感覚機能が衰え、周囲の状況を把握することが難しくなるため、これまで平気だった留守番でも不安を感じやすくなることがあります。また、認知機能の低下も分離不安の原因となることがあります。 |
| コミュニケーション不足、運動不足、愛情不足 | 普段から飼い主さんとのコミュニケーションや触れ合いが不足していたり、適切な運動ができていないと、犬はストレスを溜め込みやすくなり、分離不安のリスクが高まることがあります。ある研究では、運動量の少ない犬は分離不安になりやすいという結果も報告されています。 |
| 脳や神経の障害 | まれなケースではありますが、脳や神経系の疾患が原因で分離不安のような症状を示すこともあります。 |
犬の分離不安症は、犬種によってなりやすい傾向があることも報告されています。ミニチュア・ダックスフンド、トイプードル、チワワなどが比較的上位にランクインしていますが、犬それぞれの性格や飼育環境、飼い主さんとの関係性も大きく影響するため、犬種だけで決まるものではありません。
分離不安症の予防:子犬の頃からできること

分離不安症は、子犬の頃からの適切な関わり方によって予防できる可能性があります。
子犬の頃からの一人遊び
子犬の頃からおもちゃなどを使って一人で遊ぶ楽しさを教えることは、飼い主さんへの過度な依存を防ぎ、自立心を育む上で非常に重要です。
安心できる環境
クレートトレーニング
クレートを犬にとって安心できる安全な場所にすることで、留守番中の不安を軽減することができます。クレートの扉を開放して自由に出入りできるようにし、中におやつやお気に入りのおもちゃを入れて、クレートに入ることは良いことだと認識させましょう。また、「ハウス」という指示と共におやつをクレートの中に投げ入れて、クレートに入ることをポジティブな経験と結びつけることも効果的です。
静かな部屋
騒音や刺激の少ない、落ち着ける空間を用意してあげることも大切です。
飼い主の匂いがついたもの
飼い主さんの匂いがついたタオルや衣類などを犬のそばに置いておくことで、安心感を与えることができます。
ラジオやテレビ
留守番中にラジオやテレビをつけて、バックグラウンドノイズを作ることで、外の音に対する過剰な反応を和らげることができます。ペット専用のチャンネルなどを利用するのも良いでしょう。
カーテンを閉める
窓から見える外の刺激を減らすことも、犬の不安軽減につながります。
十分な運動と刺激
毎日、散歩や遊びを通して十分な運動をさせることは、犬の心身の健康を保つ上で不可欠です。留守番前には特に、散歩などでしっかりと体力を発散させておくと、犬は落ち着いて過ごしやすくなります。
また、知育玩具やノーズワークなどの頭を使う遊びを取り入れることも、精神的な刺激となり、分離不安の予防に役立ちます。1日に2回程度、激しい運動を取り入れると、分離不安に良い効果があるという報告もあります。
過度な依存を避ける
常に犬を構いすぎず、適度な距離感を保つことが大切です。在宅中も、犬と離れて別々の場所で過ごす時間を作るようにしましょう。
犬が遊びや撫でることを求めてきても、すぐに要求に応えるのではなく、飼い主さんのタイミングで応じるようにすることで、犬の過度な依存を防ぐことができます。また、留守番前後はもちろん、日常生活においても過度なスキンシップは避けるように心がけましょう。
留守番の練習
短い時間から少しずつ留守番の練習を始めることが重要です。最初は数秒から始め、犬が不安を示さない範囲で徐々に時間を延ばしていきます。外出する準備だけをして実際には出かけないという練習も、犬を安心させる上で有効です。
良いことと結びつける
外出する際に、フードの入った知育玩具を与えたり、特別なおやつを用意するなど、留守番を犬にとって楽しい時間と関連付けるように工夫しましょう。
外出時と帰宅時の行動
外出する時や帰宅した時に、大げさに声をかけたり、過剰にスキンシップを取ることは避けましょう。普段と変わらない落ち着いた態度で接し、犬に「特別なことではない」と理解させることが大切です。帰宅後も、犬が落ち着くまでは過剰に構わないようにしましょう。
もしなってしまったら?分離不安症の対策と治療法
もし愛犬が分離不安症になってしまった場合でも、適切な対策を行うことで改善が見込めます。
| 対策・治療法 | 詳細 | 注意点 |
| 行動療法 | 専門家(ドッグトレーナーや行動療法に詳しい獣医師)の指導のもと、段階的に留守番の時間を延ばす脱感作療法や、外出の準備に慣れさせるトレーニングなどを行います。犬の要求行動には応じない、飼い主主導で犬との接触時間を決める、「待て」のトレーニングなども有効です。外出と良いことを結びつける工夫も重要です。 | 根気強く、犬のペースに合わせて行うことが大切です。問題行動を叱ることは逆効果になる可能性があります。 |
| 薬物療法 | 獣医師の診断に基づき、抗不安薬などの薬を使用します。セロトニンを増加させる薬が用いられることが多く、フルオキセチン、クロミプラミン、トラゾドンなどが代表的です。 | 必ず獣医師の指示に従い、行動療法と併用することが基本です。自己判断での使用は避け、副作用についても理解しておく必要があります 。 |
| 安心できる環境の再構築 | 静かな部屋を用意する、クレートを快適な場所に整える、飼い主さんの匂いがついたタオルなどを置く、カーテンを閉めて外の刺激を減らす、ラジオなどをつけて音環境を整えるといった工夫を行います。 | 犬が本当に安心できる環境になっているか、観察しながら調整しましょう。 |
| おもちゃ、知育玩具、頭を使うゲーム | 留守番中に犬が飽きないように、お気に入りのおもちゃや知育玩具、頭を使うゲームなどをいくつか用意しておきましょう。特に、フードを隠せる知育玩具などは、長時間犬を夢中にさせることができます。 | 安全な素材でできたおもちゃを選び、誤飲しないように注意しましょう。 |
| サプリメント | 犬用のリラックス効果のあるサプリメント(α-カソゼピン、L-テアニン、GABAなど)も補助的に使用できる場合があります。セロトニンの働きを助けるサプリメントもあります。 | 効果には個体差があるため、獣医師に相談してから使用することをおすすめします。 |
| 専門家への相談 | 分離不安の症状が改善しない場合や、重度の場合は、自己判断せずに、行動療法に詳しい獣医師やドッグトレーナーなどの専門家に相談しましょう。重症例では、獣医行動診療科認定医の診察も検討しましょう。 | 専門家は、それぞれの犬の状態に合わせた適切なアドバイスや治療法を提案してくれます。 |
愛犬の分離不安に対して、問題行動を叱ったり、無理に閉じ込めたりすることは、犬の不安を増大させる可能性が高いため避けるべきです。また、不安な時に過剰に慰めることや、外出前に大げさに声をかけることも、逆効果になることがあります。
まとめ:愛犬の笑顔のために

犬の分離不安症は、多くの場合、飼い主さんとの強い絆があるからこそ起こるものです。愛犬が飼い主さんと離れることに強い不安を感じてしまうのは、それだけ飼い主さんのことを大切に思っている証拠と言えるでしょう。
早期に適切な対応を行うことで、分離不安症は改善できる可能性が高い病気です。愛犬がお留守番中も穏やかな気持ちで過ごせるように、それぞれの犬に合った対策を見つけていきましょう。
もし困ったことがあれば、ためらわずに専門家の力を借りて、愛犬とご自身が共に安心できる方法を探してください。