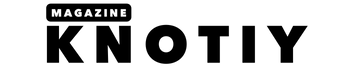「うちのわんこ、たまに自分のうんち食べちゃうんですよね…」という相談をよく受けます。
犬を飼っていると、時々ギョッとするような行動を目にすることがありますよね。その中でも、自分のうんちや他の動物のうんちを食べる「食糞」は、飼い主さんにとってかなり衝撃的な光景かもしれません。実はこの行動、犬にとってはそれほど珍しいことではなく、多くの飼い主さんが経験していることです。
今回は、ワンちゃんがうんちを食べてしまう「食糞」について、その原因を医学的な面と行動学的な面から、そしてそのリスクと具体的な対策まで解説していきます。もしあなたの愛犬がうんちを食べることに悩んでいるなら、ぜひ最後まで読んでみてください。
なんで犬はうんちを食べるの?

犬がうんちを食べるのには、色々な理由が考えられます。大きく分けると、体の病気が原因になっている場合と、行動の理由がある場合の2つが考えられます。それぞれの理由を知ることで、より良い対策が見つかるはずです。
体の病気が原因でうんちを食べてしまうパターン
まずは、わんちゃんの体に何らかの異変があって、うんちを食べる行動に出ている可能性を考えましょう。もし心配な場合は、自己判断せずに獣医さんに相談するのが一番大切です。
栄養が足りないケース
ドッグフードの質が良くなかったり、必要な栄養素が足りていないと、犬はうんちから不足している栄養を摂ろうとすることがあります。特に、ビタミンB1(チアミン)が足りないと、食糞につながるという研究あります。ただ、市販されている質の良いドッグフードは、通常犬に必要な栄養バランスを満たしているので、はっきりとした栄養不足はあまりないかもしれません。もし手作り食や生の食事を与えている場合は、栄養バランスが偏っていないか注意が必要です。
お腹の調子が悪い?
消化酵素がうまく出ていなかったり(特に膵外分泌不全(EPI))、お腹の中で炎症が起きていたり(炎症性腸疾患(IBD))、腸内細菌のバランスが崩れていたり(小腸内細菌過剰増殖症(SIBO))すると、栄養がうまく吸収できなくなって、食欲が増し、うんちを食べるようになることがあります。また、うんちに未消化の食べ物がたくさん含まれていると、その匂いや味に惹かれてしまうこともあります。
寄生虫がいる?
お腹の中に寄生虫(回虫、鉤虫、鞭虫など)がいると、寄生虫が犬の栄養を横取りして、栄養不足の状態になることがあります。その結果、犬はうんちを食べることで、足りない栄養を補おうとすることがあります。特に、うんちの中にいる寄生虫は、食糞によってまた体の中に入ってしまうことがあるので注意が必要です。
年を取って認知機能が低下?
高齢の犬では、認知機能が低下(犬の認知機能不全 – CCD)することで、食糞をしてしまうことがあります。これは、人間でいう認知症のようなもので、今までできていたことができなくなるケースです。
薬のせい?
ステロイドなどの特定の薬は、犬の食欲を異常に高めることがあり、その結果としてうんちを食べる行動につながることがあります。抗てんかん薬も食欲を増進させる可能性があります。
行動や心理が原因でうんちを食べてしまうパターン

体の病気が見つからなかった場合は、犬のうんちを食べる行動は、行動学的な理由によるものと考えられます。特に子犬によく見られる行動ですが、大人になっても続くことがあります。
お母さんのマネをしている
出産後の母犬は、子犬の排泄物を食べることで巣を清潔に保ち、外の敵に子犬の存在を気づかせないようにします。子犬はこの母犬の行動を真似ることがあります。
好奇心旺盛
子犬は何でも口に入れて確かめることで、世界を探検します。うんちもその対象になることがあるんです。多くの場合、成長するにつれてこの行動は自然に減っていきます。
退屈やストレスを感じている
長時間のお留守番や、運動不足、遊びの時間が足りないと、犬は退屈やストレスを感じて、その解消としてうんちを食べる行動に出ることがあります。
不安な気持ちを感じている
過去に排泄の失敗を叱られた経験のある犬は、排泄の痕跡を隠すためにうんちを食べてしまうことがあります。
注目してほしい、目立ちたい
犬は飼い主に注目してもらいたいという気持ちから、うんちを食べるという問題行動を起こすことがあります。特に、飼い主が過剰に反応する場合、犬はその反応を得るためにこの行動を繰り返すことがあります。
味や食感が好き
うんちに含まれる未消化の脂肪やタンパク質などの匂いや味が、犬にとって魅力的に感じられることがあり、新鮮なうんちを好む傾向もあるようです。
他の犬のマネをしている
他の犬がうんちを食べているのを見て、真似をする可能性があります。多頭飼育の家庭でよく見られることがあるようです。
うんちを食べるとどんなリスクがあるの?

犬がうんちを食べる行為は、私たち人間からすると不快なだけでなく、わんちゃんの健康にも良くない影響があります。
寄生虫に感染するかも…
うんちには、回虫、鉤虫、鞭虫、条虫、ジアルジア、コクシジウムなど、色々な寄生虫の卵や幼虫が含まれている可能性があります。これらの寄生虫は、下痢や嘔吐、体重減少、貧血などの症状を引き起こすケース。うんちを食べることで、これらの寄生虫に感染するリスクが高まります。
お腹を壊す可能性も
うんちには、犬の消化器系に合わない物質や細菌が含まれている可能性があり、嘔吐や下痢などの消化器系のトラブルを引き起こすことがあります。特に、他の動物のうんちには、犬にとって有害な細菌がいる場合もあるので注意が必要です。
感染症のリスクも
うんちには、大腸菌、サルモネラ菌、カンピロバクターなどの細菌や、パルボウイルスなどのウイルスが含まれている可能性があり、これらに感染するリスクがあります。これらの感染症は、犬に重い症状を引き起こすことがあるので注意が必要です。
人にも感染する?
犬がうんちを食べた後、飼い主さんを舐めるなどの接触を通じて、犬の口の中にいる細菌や寄生虫が人に感染する可能性も否定できません。特に、免疫力が低い人や子供は感染しやすいと考えられています。
どうすればうんちを食べるのをやめさせられる?

愛犬がうんちを食べるのを見つけたら、まずは動物病院で診察を受けて、体に原因がないか確認することが一番大切です。獣医さんは、犬の病歴や普段の食事、生活環境などを詳しく聞いて、必要であれば血液検査やうんちの検査などを行うことがあります。原因を特定して、それに合った対策をすることが大切です。
体に原因がある場合の対策
もし体の病気が原因だとわかったら、その病気に対する治療を行います。
犬がうんちを食べないようにする対策
- 食事を見直そう
栄養バランスの取れた質の良いドッグフードに変えてみましょう。消化吸収が悪い場合は、消化しやすいフードや、脂肪分が少なく食物繊維が多いフードが良いかもしれません。獣医さんや栄養士の指示に従って、適切なフードを選んであげてください。 - お腹の治療を
消化酵素が足りない場合は、消化酵素を補う治療を行います。寄生虫がいる場合は、駆虫薬でしっかり駆除しましょう。その他の消化器系の病気の場合は、それぞれの病状に合わせた治療が必要になります。
行動が原因の場合の対策
行動が原因と考えられる場合は、生活環境を改善したり、しつけを見直すことことが大切です。
生活環境を見直そう
毎日十分な運動や遊びの時間を作って、わんちゃんのエネルギーを発散させてあげましょう。退屈しないように、知育玩具などを活用するのも良いです。
トイレはいつも清潔に
うんちをしたらすぐに片付けるようにすることで、犬がうんちに近づく機会をなくしましょう。お散歩中も、排泄したらすぐに拾って持ち帰りましょう。
「待て」を教えよう
「待て」や「離せ」などのコマンドを教えることで、うんちに近づこうとしたときに制止できるようにします。できたらたくさん褒めて、ご褒美をあげてください。
食糞防止剤を試す?
市販の食糞忌避剤をうんちにスプレーしたり、フードに混ぜたりすることで、うんちの味をまずくして、犬が食べるのを防ぐ効果が期待できます。獣医さんに相談して、愛犬に合ったものを選んでみてください。
無視することも大切
うんちを食べるのを見ても、大げさに反応せずに、落ち着いて対処することも大切です。騒いだり、叱ったりすると、犬が注目を集めようとして、さらにうんちを食べる行動を繰り返す可能性があります。
食事の与え方を工夫する
早食い防止用の食器や知育玩具を使うことで、食事の時間を長くして、満腹感を得やすくします。食事の量や回数、フードの種類を見直すことも有効かもしれません。
まとめ
犬の食糞は、色々な原因が考えられる複雑な行動です。もし愛犬がうんちを食べるようなら、まずは獣医さんに相談して原因を特定することが重要です。その上で、体の病気が原因なら適切な治療を行い、行動が原因なら生活環境の改善やしつけなどを根気強く行いましょう。
飼い主さんの愛情と正しい対応で、きっと愛犬の困った食糞の習慣も改善できるはずです!